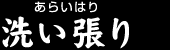 |
|
反物を洗い、幅や長さを出すことを張るといいます。
着ていたものが、何年も経って汚れたり、しみが出てきたら、きものは縫い目を解いて洗うことが出来ます。
袖、身頃、おくみ、衿を縫い合わせて、一反の反物に戻します。(一反の長さは約13.3m)
その反物を水やぬるま湯の中で洗剤を使い、洗い張り専用のブラシできれいに汚れやしみを洗い落とします。勿論、裏地も同様に出来ます。
次に、反物は水やぬるま湯に浸けると縮む性質があるので、幅や長さを元の寸法に戻す為、左右に引っ張って出します。反物には糊が付いています。洗うことによって古い糊が洗い落とされ、新しく糊入れをすることで、絹独特の艶、張り、しなやかさが再現できるのです。
|
|
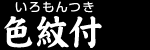 |
|
| 無地(一色)に染める前に、紋糊を置き、浸染又は、引き染めで染めたあと紋章上絵をする。一つ紋、三つ紋、五つ紋があるが、おもに一つ紋が略礼装として用いられる。 |
|
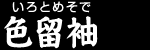 |
|
| 宮中で主に用いられており、叙勲などで参内する人の礼装としても着用される所から徐々に一般の礼装に取り入れられてきた。略式礼装との誤った捉え方から一つ紋、三つ紋でも良いとする説があるが、黒留袖と同格であり、五つ紋で重ね着(比翼仕立てが多い)が正式である。 |
|
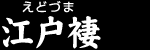 |
|
両褄模様が江戸文化(大奥)で形式化され華美になったとされ、江戸褄といわれるようになった。黒地の裾模様(留袖の項参照)
|
|