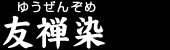 |
|
| もち米を原材料とする防染剤(糊)を使用し、下絵に沿って筒描きで糸目(線描き)を置き筆や刷毛で、染料を差し彩色する技法。糊を置かないで、直接染料や顔料で模様を描く無線友禅。型紙を使って糊置きや色差しをする型友禅などもある。留袖や訪問着などの絵羽模様を染める。(模様染色の項参照) |
|
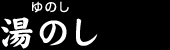 |
|
絹の生地は湿気をすったり、水に浸けたりすると、布巾が縮んだり、しわがでます。
生地を染めて水元(流れる水で染めのりを落とすこと)したり洗ったりしますと幅も丈も縮みます。この布に蒸気を当てて、巾を整えることを湯のしといいます。 |
|
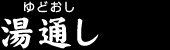 |
|
| 絹織物は機で織ったままでは、糊気(織る前に糸に糊をつけて織り易くする)が残っていて、しなやかさが無く、また布目も通らず、表面の光沢も悪いので、お湯(ぬるま湯)に浸けて糊を落とし、張ってから湯のしをすることによって、着物として仕立てられる状態になります。このことを湯通しといいます。 |
|