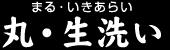 |
|
きものは仕立てあがった状態で洗うことが出来ます。(水では洗えません)
丸・生洗いは 東京きもの染洗協同組合の登録商標です。 |
|
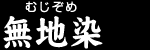 |
|
| 白生地又は抜き地を色無地に染めること。(浸染、引き染めの項参照) |
|
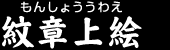 |
|
およそ7,500種以上はある家紋(紋章)。日本独特のものでデザイン的にも世界に誇れるものです。
そんな紋を紋墨といわれる墨で指定された家紋の形に筆で描き上げる仕事をする人。紋糊(紋糊置き業 参照)を落とすことは勿論のこと、汚れた紋を洗って描き直すことや、古い紋を消して違う紋を描く、また、消えない紋は切り付け紋といって、別の生地に紋を描いて切り抜き、糊張りをして糸でかがる。染まっている生地の場合は、紋抜きといって紋の大きさに色を抜き、紋を描き入れる。 |
|
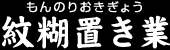 |
|
| きものに紋を染め抜く場合、白生地に紋糊(ゴム糊)を置いて、紋の部分が染まらないようにする。紋型(それぞれの家紋の外形を渋紙に彫る)を使用する。 |
|
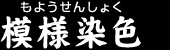 |
|
きものに模様を描き染める人。無線友禅(素描)といって直接生地に描く方法もあるが、友禅染めは、白生地に藍花といって水溶性の藍色を使って、筆で模様の下絵を描く。模様の大きさ、配置などが決まれば(この段階では、藍花は水で消せるので訂正できる)筒で下絵に沿って糊置きをする。
訪問着や留袖などは、仮絵羽(きものの縫い合わせの部分の柄を合わせるために、顧客の寸法に仮縫いをする。)してから仕事をする場合が多い。
糊で防染(糸目糊置き)された中に、筆や刷毛で染料を差して模様の彩色をし、彩色が終わったら模様の部分を糊で伏せ、引き染めで地色を染めて、蒸し、水元(友禅流し)、仕上げ、金、銀加工をして仕上がる。全工程を一人でやる人もいるが、多くは柄を描く、色を差す、金、銀加工ぐらいで、後は分業で行われる。しみ痕加工、彩色直しなどの仕事もしてくれる。染め問屋や悉皆屋をとおしての受注。
|